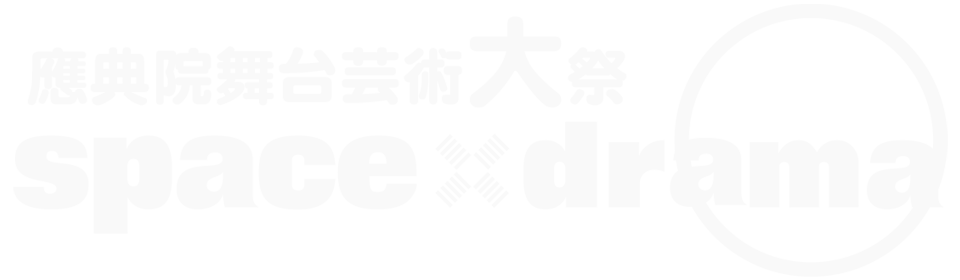【遊劇舞台二月病『Round』】転げ落ちていくRound 【泉寛介(baghdad café 脚本・演出)】

生活保護ケースワーカーのルポルタージュを見ているような演劇だった。
演劇的な工夫として、主人公をパチンコ依存症という設定に置き、そのパチンコの「演出(リーチ中アクション)」として生活保護受給者の複数の物語を見せるという構造になっている。この複数の物語は、無作為にリーチ演出が来るパチンコのように断片的にシャッフルして語られるだが、その内容が現実的であまりにも不遇な境遇なので、見ていて心がしんどくなってくる。その一方で、こういった現状があることに対して自覚を持つことを強く考えさせられる観劇体験だった。
若くして授かり婚となる娘の顔合わせ食事会のために金欠の元父親は自身と同境遇の娘のためちっぽけなプライドも手伝ってCRケースワーカーというパチンコに手を出す。その遊戯中、彼は彼自身が目の前で助けたくても助けられなかった人々への悔恨を再確認し、職を離れた5年間独自で勉強した成果をもって彼らを希望へ導く。彼はヒーローになるはずだった。遊戯を終え、店を出たところで元妻と再開しパチンコのことを詰られる。その関係も希望が見えるように映っていた。
観客としてはラストの展開が二つの意見に分かれるように思えた。物語として享受する=虚構として受け取るなら、観客にとって希望の見えるラストであり、道中が苦しければ苦しいほど、最後のカタルシスが強度を増すようになっているように思う。妻との復縁までは見込めないが、良好な関係で推移するだろうと予測できる店を出た元夫と元妻の会話や、DVの疑いを掛けられていた男が、亡くなった子供のことを乗り越えるべく「これから」と希望を見出すところなど、ポジティブに見え、納得もできるだろう。
一方、冷静な視線=現実的な見方で見てしまうと、一人のギャンブル依存症(というほどでもないが)の男がパチンコに熱中しながら自身のこれまでのケースワーカーとしての仕事を悔恨し、自己完結する妄想でしかない、という見方もできる。仕事のことがメインになり、自身の家族に対する反省は見えなさそうな回想でもあった。
そうなるとラストのポジティブな展開は非常にご都合主義に映ってしまう。それまでの生活保護受給者たちの困窮する姿が鮮烈にリアルなため、最後の展開を余計に生ぬるく感じてしまう。それは転じて、各生活保護受給者たちのリアルに描かれているしんどさが一層際立つことになる。つまり男にとっては希望のあるエンドかもしれない(それも単なる甘い妄想かもしれない)が、現実にはそんな簡単に行くはずがない、そういった生活保護受給者の苦しい現状に意識的になるべきという教訓めいたものを観客に残す装置にもなっている。
観客にとっては苦行のような観劇体験となる。自分に何ができるのか、いや何もできない、などのある種のサバイバーズ・ギルトのような感覚を持ち続けさせられる。通りすがりに道端で倒れている浮浪者を観た感じ、そういったような、現実に起こっている深刻な問題に対する、僕らの普段忘れてしまっている態度を促される。
根本となる脚本、演技はリアルであることを求め、転換や一部の身体表現は虚構のような脚色を創り、表層の部分を覆う音響照明は好意的に観客と結び付けようとする。そのようにやや、小出しにエンターテイメントされているため、観客は救い(ほっとするシーンや「快」を得られるシーン)に焦らされ、求めるように舞台を見つめる構造になっていたのではないだろうか。
美術配置や美術そのもの、ミザンスには技術的甘さ/飾らない素朴さも見える。ややちぐはぐな印象を受ける。だが少し萎びたパチンコ店のなんとも言えない虚飾的な感覚にも似ているような気はした。座り芝居も多いため、ストレスは多少なりともある。その場に在る、ということが目的なら客席、ミザンスには気をつけたい気もする。
考えたくない(本当は考えなくちゃいけない)物事をズンズンと突き付けてくる。一番響くのは身内に該当する当事者がいる場合だろう。もう見ていられないのではないという方もいるのではだろうか。そういった作品に何も意味が無いことは無いと思うが、非常にセンシティブな部分なので様々な反応があるだろうと思った。それも含めてどのようなイメージで劇団が執拗に取材し、この作品を創ったのも気になる作品だった。
観客と寄り添うような簡易避難所のような枠組みは作られているものの、前半から物語の構造を掴むまでにやや時間があるので、その重いモチーフを続けられることを見続けるには体力がいる。だが、それを推して、遊劇舞台二月病は淡々と訴え続ける。
その源流には観客に常に問い続けるとても大きな意識が流れているようだった。この惨憺たる物語を虚構として見られてはいけない、という矜持なのだろうか。その原動力はある種とても不気味でその分、奇妙な魅力(といっていいのか、目を離せない何か)を持った作品だったように思う。救いの無い他者の状況に対しての自分が何もできないというそのできなさの前で敬虔な修行僧のようにじっと禅問答を繰り広げている。
死んでしまった人はもう蘇ることはない。骸骨の舞跳は関東大震災後の避難所で朝鮮人の虐殺に、当時の日本人に対して異を唱える日本人の叫びのような作品だった。それを参考にしたこの作品のパンフの挨拶には、ギャンブル依存症への警鐘に関する言葉が連なっていた。IR誘致やカジノ依存症対策の問題、パチンコ依存症、この作品の根幹はそこではない。
この貧困や格差社会というシステム、ふと気づけばだれもが階段を知らぬ間に転げ落ち、そこからは緩やかに詰んでいく社会の構造、そういったものに関して彼らなりに、静かに、そしてがむしゃらに気を吐いている部分で繋がっているように思えた。回り続ける思いの圧が應典院に充満していたようだった。
6月23日19時半の回に観劇。