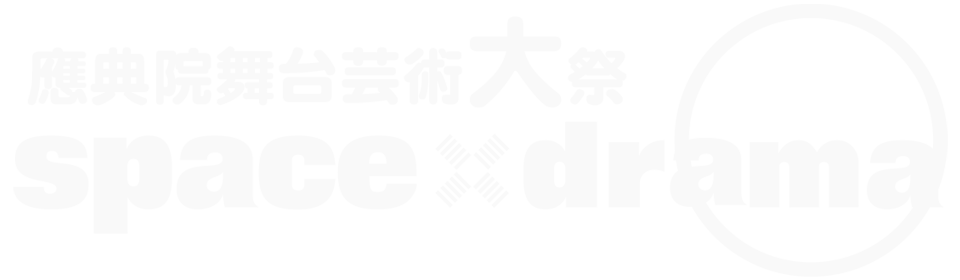【May『ハンアリ』】感想【 CQ/ツカモトオサム】

いつもMayを見る中盤の頃に「長い」と感じる。
2時間で終わった試しがない。
以前は3時間を超えることだって在った。
だが内容を振り返ると不要なシーンはほとんど無く、観客が誤解なく作品を受け止める細心の心配りが為されていることを痛感する。
終盤に入ると既に瞳は潤み、不覚にも涙が零れている。
もう「長い」ことなど、どうでも良くなってしまう。
これまでの作品で、作者の金哲義氏が自らの実生活で経験したコトや、両親や曾祖父母から伝え聞いたコト、家族や友人の体験談を基に、限りなく実話に近い物語として構成して来た多く舞台作品は、常に嘘のない真実の投影であり、そこにはその時代を確かに生きた人たちが描かれてきた。
それを見る私たちは国籍や人種や人を区別するあらゆる境界を越え、家族を思い、友を想い、時代に翻弄されながらもひたすら悪戦苦闘し、ただただ懸命に生きる人々の姿に心を打たれ、目頭を熱くする。
本作は京都に実在する高麗美術館を建てた館主チョン・ジョムンの生涯を描いたノンフィクションであり、自身の内側から派生する普段の金作品とは観点が大きく異なる。
付かず離れずジョムンを見守る視点から物語は構成され、目立つ違いはその1点に尽きる。
しかし視点をどこに据えようが描こうとする物ごとに全くブレはなく、つまりいつものMayそのものである。
短いシーンの集積、場面転換は暗転を用いず全てシルエット転換で処理する。
まるで高校演劇かと思えるほど、常に同じ手法を用いる。
暗転を多用し間延びするよりは、場面転換を明転(あかてん・最近は[めいてん]とも・見せる転換として[見せ転]とも呼ぶ)処理するのは英断である。
高校演劇では暗転中の事故防止のため、暗転を禁止し舞台全体をフラットなブルーに染め、転換を全て青転(おおてん・明転の一つ・ブル転とも)処理する大会も見掛ける。
シルエット転換(略してシル転)は転換中の登場人物が誰か判らないように後方からの照明で観客に舞台上の人物が識別できないよう工夫された転換で、青転よりはバリエーションを設けやすくて見栄えも良く、もちろん高度なのだが、青転のバージョンアップと言える。
青転は、ホリゾントのみに明かりを入れて登場人物を完全な影だけにして転換するホリゾント転換(ホリ転)と共に、高校演劇の場面転換に於ける主な転換方法として定着し、ある大会で高校生が皆これを「ブルー暗転」と呼ぶのを耳にした。
この名が所々で定着しているようで、どうにもむず痒くて仕方がない。
暗転でない転換、つまり観客から見える転換は全て明転である。
よってブルー明転とは言えるが、ブルー暗転はあり得ない。
身内で慣用的に用いるのは自由だが、演劇人は後進のため正しい演劇用語を使いたい。
話は戻る。
93年に旗揚げしたMayは、80年代から90年代に掛けて確立した多くの転換法の中から最も安全性の高い転換法を選び、時代の変化に日和ることなく、このスタイルを完成形とし、今もこの様式を貫く意志の強い集団で、その芯の強さ故かこの転換法が作風とも非常に良く合っている。
進化はしないが進歩は止めない姿勢に全く迷いがないのも素晴らしい。
もちろん、暗転や他の転換法も必要に応じて選択する柔軟性も在るのは当然ながら、ベーシックが解りやすく明確なのだ。
本作で最も好きな挿入話は、昔話で朝鮮と中国を隔てる川が冬になると凍って陸続きになり、両国の子供たちが何の隔てもなく川を渡り一緒に遊んでいたと言う件で、韓国籍の無いジョムンが九州よりも朝鮮半島に近い対馬に渡り、目前に見える故郷をどれだけ恋しく思えど航れぬ思いを、故郷の代わりとして建てた美術館に託すことになる。
造るコトより維持するコトはより難しい。
始まりと終わりが想定された、時間に区切りのある創造よりも、期間限定でない創造物を無限の時間維持するには想像を絶する苦労がある。
これは図らずも一つの演劇祭の維持と終焉の顛末にリンクする。
いつかはこの小さな方舟が白い壺に描かれた大船の如く、荒波の玄海灘を越え、対馬海峡を渡り、北も南もない本当の故郷へと漕ぎ着く渡し船になるようにと、ラストシーンの転換でジョムンの願いが象られ、舞台は美術館から客席をも含む大船へと姿を変え、大海原へと出航する。
美しく見事なラストシーンであった。
多くの劇団を載せながら十余年を掛けて築き上げられたspace×dramaが、どのように姿を変えて維持され、この先何処に辿り着くのか今はまだ知れないが、そこにまた私たちの故郷を感じたいと思う。
故郷に思いを馳せ逝去したジョムンの姿が、今月いっばいで勇退する森山氏に重なり、感慨も一入に深まった。