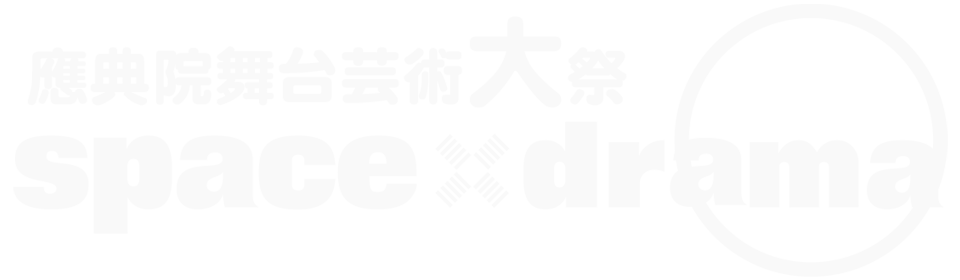【May『ハンアリ』】 物語と歴史の二面性 【泉寛介(baghdad café 脚本・演出)】

同郷を持つ同胞にも関わらず、対岸同士のような関係をいくつかの軸で見せられる。在日コリアンと朝鮮半島にいる韓国・朝鮮人、在日1世と2世、そしてジョムンとフィソン・リョンエのような親子。その隔たりは対馬から見た朝鮮半島のように、近く感じることも、現実的に遠いこともある。対岸へ祈りを遣る視線によって、様々な思いが想起されて胸が熱くなった。
演劇の構造としては物語を伝えるツールとしての演劇のように感じられた。高麗美術館を開館した鄭詔文さんのドキュメンタリー映画を元にした作品、それをストレートに演劇化しているようだった。だから当然、内容的にもそうだけれど観劇感としても、テレビや映画のドキュメンタリーを見ているような感覚だった。
ドキュメンタリーと言う手法はカメラや記録する側のバイアスが入るため、事実と異なる可能性をはらんでいる、とソニル役として登場した金哲義さんは語った。それは在日1世が聖人のように語られることを嫌がるフィソンの心情にリンクしていく作りだった。
劇の大部分を占める回想は、ジョムンが民族としてのアイデンティティを獲得しようとした原体験に始まり、若き同胞たちに広めるため尽力するまでのまさに民族にとっての聖人のような姿と、一方でフィソンやリョンエの視点から見た家族を振り回す独善的で身勝手な姿の二面性が同時に描かれる。
対馬にてフィソンがジョムンと同じ風景を見るシーンで、ジョムンの人生を残念と思ったか、誇りに思ったか、それとも様々な思いが混ざりあったのか、とにかく昂ぶったフィソンの姿を見ると、父への許し・哀れみ・共感のような態度が見えた。リョンエの頭をおそらく初めて撫でたであろう瞬間も同様に思われた。それはジョムンの背景を2時間追ってきた観客である私たちにも共鳴する。
日本に渡来し、特高警察の監視下におかれ、同級生に迫害を受けていた極貧の生活、マラソン大会での敢闘、戦争下の軍需工場、戦後のパチンコ屋経営、李氏朝鮮の白磁器との出逢いによって余計に募っていく故郷でのそり遊び、自身のルーツへの探求からナショナリズムへの発展、家族や娘婿までも振り回して美術館を作るに至るまで、そんなジョムンの半生が走馬灯のように観客の胸にも去来する作りになっている。何度もリフレインされる、在日としての自身への問いや煩悶(「負けたくないのか、勝ちたいのか」「これからもずっと小さい存在のままでいいのか」「海が凍ればそりで向こう岸まで渡れるのに」)が思いの厚みを増していた。
一方、父ジョムンの視点で描かれている物語だからどうしてもジョムンに肩入れし、家族の苦しみは少なく感じてしまった。誰かを振り回している人はドラマもあって魅力的だ。けれどその振り回された人々、後の処理をする人々は地味だけれど、とても現実的で大変だ。そんなことも少し考えた。まあでも物語であるなら、これはこれでよいか、とも思った。
そういった父と子の隔たり、在日コリアンの葛藤の物語、ドキュメンタリーの持つ視点のバイアスという物語の軸で楽しみつつも、一方で端々に出てくる時代背景がどんどんと胸にのしかかってくる感覚があった。この物語の背後にある歴史という軸だ。
韓国併合や強制連行、在日コリアンにならざるを得なかった人々の暮らし、第二次世界大戦、そして朝鮮戦争によって分断された故郷、そういった歴史に関するセリフや場面がボディブローのように国民性を揺るがして、考えさせられた。教科書やメディアのレベルでしか知らなかったことが肉感を持って伝えられる。狂言回しがやや説明過剰だなと感じるところがあった。だけどそれは仕方がない。ある意味、そういう作りでないと説明しえないという現状もあるのだろう。それはまたなんともいえない気持ちになる。
特徴的に覚えていたのは、構成作家グァンヒとフィソンの会話で、在日コリアンのことを朝鮮半島にいる人は何も思っていない人も少なくなく、むしろ存在を知らない人もいる、ということだ。なんと切ないのだろうと思ってしまった。ただ、逆の立場で言えば、僕は残留孤児や日系ブラジル人の生活や歴史を詳しく知らない。そう考えると、そんなものなのかもしれない、と妙に納得してしまった。この納得はなんなんだろうと考えた。そこにはやはり当事者との隔たりが存在する。
ふと学生時代の友達、Kちゃんのことを思い出した。確か彼が成人になるくらいに帰化するかどうするか、迷っていたという話を聞いたことがある。性格的に勝気で陽気な彼は確か在日三世だったように記憶している。その親父さんがまた豪快な人で、その勝気な(というかやんちゃな)彼もその親父さんにだけには頭が上がらない感じだった。僕たちは普段ちょけているときに、「調子乗ってるとMさん(Kの親父の下の名前)に大阪湾沈められんぞ」、なぞとKちゃんと一緒にMさんをいじって笑っていた。
そんな感じで実は身の回りにいたあの人たちの親や祖父母が同じような状況だったかもしれないということを、恥ずかしながら観劇後に気づいた。Mさんの豪快さはある種の逞しさだったんだろうな、なんて思った。
当事者への距離感は気づきによって見方が変わる。領土問題や慰安婦問題、拉致問題など、そういった視点を持つことで見え方も変わってくる。それは親と子、そしてそのさらに下の世代まで、コミュニケーション全般においてもそうだ。文脈を知らないところから対話は始まる。僕にとってはそんな頭では当たり前だと思っていたことを体で分かるように気づかせてくれる作品だった。
6月18日(日)14時の回に観劇