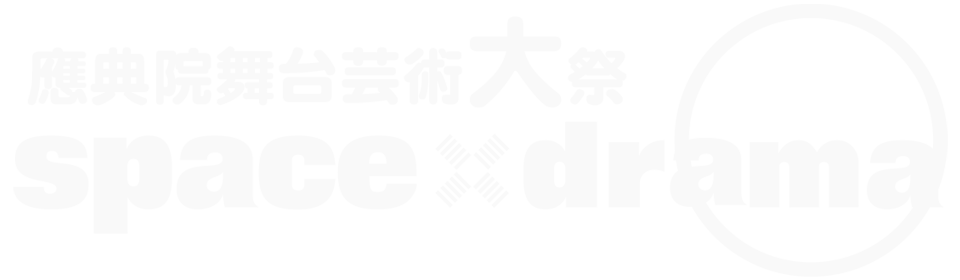【満月動物園「レクイエム」】優しい手つきで暴力を 【泉寛介(baghdad café 脚本・演出)】

見終わったあと、内容的に少し重い気持ちもあったけれど、希望のような感情が心に残った。大きな要因は物語のラスト、本堂ホール奥下手の窓が開け放たれて劇場が外の空間とつながる。窓の「ガパ」という音が少し聞こえて、密閉空間が緩んだような感じを受けた。その感じは、チェーンソーのオイルの匂いや、怨念のようなハマダ、雲雀、イシバシなどの情念や血とカレーの匂い、それに役者の熱で充満していた劇空間を日常に戻す。脳が現実に引き戻されて虚構と現実の曖昧な悪夢にうなされていたところから目が覚めたような感じがした。
また同時に、丸尾丸一郎さんの脚本を満月動物園の手法で公演するとこうなるのか、という発見が強く残った観劇だった。終演後、それをもやもやと考えていた。
物語の要素としては、猟奇的殺人のシーンやいじめのシーン、監禁状態による発狂シーンなど見るのが辛くなるだろう場面も多々ある。満月動物園はそれらの場面に、行動原理を踏まえた演技や、視覚的に美を感じるような見せ方、状況に希望の光を持たせるような演出を使って、観劇の後味をマイルドにさせていた。
正直なところ、最初はそのマイルドさと暴力的な脚本の言葉を発する俳優にズレのようなものを多少感じた。路線の違う劇団のコラボ作品だから当たり前だろうし、満月動物園の過去公演も見ているのでその先入観があったといえばそうなのだけど、ただ、そのズレは単なる破綻ではなく、そのズレも飲み込んで特殊な形で結実している、というような不思議な感覚もまた得ていた。脚本と演技法の珍しい結びつきに新鮮さを感じていたのだと思う。
ここ近年の満月動物園、死神シリーズは悲劇やネガティブな事象に触れる手触りがとても優しかった。物語の構成が、大きな悲しみをどう乗り越えるかを重ねていく描き方をしていて、それに寄り添うような形で演出、演技はストレートに、丁寧になされていたように思う。俳優の演技は表出や状況を提示するだけではなく、内面を操作して、いかに、その場に存在しているかのようなリアリティを持った言動の表出を作り、さらにそれを丁重に観客に届けるかに注力したやり方だった。そのやり方は物語とリンクして慈善のような暖かみがあった。
今回の脚本の構成はある意味逆で、最後にカタルシスが現れるものの基本的には全編通して攻撃的な状況で負の感情の暴発が起こり続ける。この手の物語の作劇の常套手段としては、バイオレンス性を極限まで高め続けて、その勢いで観客を巻き込んでいくという手法がある。けれど満月動物園はそれを選んではいなかった。
死神シリーズ以前、かつての満月動物園で暴力的、衝撃的なシーンはあった。その当時はそれを下地に「退廃的な美」を振りかざして観客を巻き込むやり方を見せていたように記憶している。だからこの手の見せ方も満月動物園には可能だったと思われる。けれど全面に押し出していた演技手法は、死神シリーズのような丁寧さを持った手つきだった。もちろん制作状況の諸々はあるだろうけれど、それを選択したことに意図はあるように窺われた。
今作品の演技は、情緒部分を操作して表現の過激な上層レイヤーに対して、下層レイヤーに叙情的な下地を厚めに塗るという演技法がとられていたように思う。俳優は各登場人物が狂気的状況になるため、そこへ行かざるを得ない心情をいつも以上に処理しなくてはいけない。この俳優にとってやりがいもあるが大変な作業は、最終的に表面的には暴力的でありつつ、どこかしら、ほんの少し違和感を残している演技を生む。記号的であることに終始しないその演技は、一部無駄のある(ノイズ情報を含む)日常の言動に近くなる。
そういった演技を取り入れることは、暴力的な表現を生理的に、また信条的に受け入れない観客にも、ストレートな表現よりも寄り添えるようになる。俳優が女優メインであることも成果に加担しているように思えた。
満月動物園はさらに、そうしてできた演技を崩さないことを前提に、かつ脚本のダイナミズムが殺がれないようにと、ザッピング感のある映像、舞台装置への配慮、歌唱、それらをラッピングするような照明効果などを有機的に補完し、一つの作品としてまとめていた。
つまり、演技の内面と外面の両極性、エンターテイメント空間としてのパッケージングという組み合わせだったように思う。そういった演劇構造が、低いレベルでなく機能していたので、劇全体にはズレを感じてしまっているものの、結実している、という不思議な感覚を持ったのだと思う。黒猫(或る女)のピュアで正直なダンスの身体が、虚構的人格の暴力や希望の隣で断続的に細いラインを保ち続けていたのも特徴的だったと思う。
一方、そういった虚構と現実の間にある演技法や演出法で、境界を曖昧にすることは、新たな影響を生んでいた気がする。それは本来虚構であれば、虚構だからと、考えず処理できてしまう非倫理的な要素への批評的態度だ。
カニバリズムや猟奇的殺人、虐待、いじめやマウンティング、人種・職業差別、遺体や不具への不敬な態度など問題意識化できる要素が物語に含まれていた。今作品の構造上、そういった非倫理的なものへの観客の態度が、やや敏感になる方へベクトルが動くような構造になっていたのではないかと思った。劇という虚構から現実に戻って何かを考えたり、一段階踏み込んだりさせてしまう構造を含んだ手法な気もした。緩やかな転換や、戯曲の飛躍する感情造形にも想像する余白があることも、そのあたりへの想像力に手助けをする。
ノイズやズレは疑問を生む。劇中も観劇後も何かを考えるきっかけになる。上記の演技法と演出法によって、記号的に処理されがちな加害者にも相応の理由が見えやすくなる。その構造は、その加害者と被害者と傍観者の置かれた状況を複雑にもするし、深みを持たせる。
娯楽のみを受け取りたい観客ももちろんいるし、それは必然な見方だ。そちらでも応えられるようなパッケージングをしている本作品けれど、一方で、應典院の理念や事業に近い雰囲気も内包している。よく生きるため、豊かに生きるための身構えのような態度だ。
先述の窓の使用、本堂壁面を幕で全て隠さない白壁と金柱の露出など建物・空間への意識の向け方など、本堂であることや理念を含め應典院という場をロケーションとしたサイトスペシフィックな作品であるとも言える。観客は演劇を愉しみつつも、時には現実の誰かや何か、また哀しみに思いを馳せる。
葬式をしないお寺で詠われた鎮魂歌は供養と言える。ハマダヨウコと、世間から仲間はずれにされてしまったハマダヨウコのような、現実にいるドコカノダレカの情念もいっしょに供養させていたかもしれない。
6月10日19時の回に観劇。