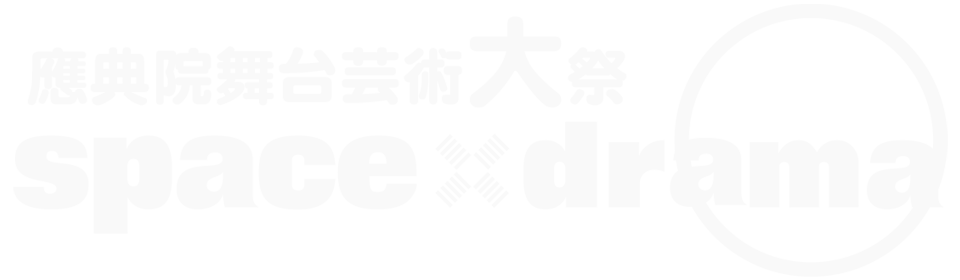【コトリ会議『あ、カッコンの竹』】 ひとさじ程度のあたたかい音 【泉寛介(baghdad café 脚本・演出)】

日常的な朝の台詞が際立って、とても切なくて美しく愛おしく見えた。それはその他の不条理な人物やシーンだったり、竹やぶの暗さだったり、死のにおいが漂う暗い世界にフッと現れた、朝陽のようだったからかもしれない。
「あ、カッコンの竹」は単純な感想としておもしろかった。山本正典さんの書く笑える対話や、抒情的なセリフ、宇宙人や野お母さんなど独特で不思議なキャラクター、普通なのにやたら無邪気に残酷だったり残念だったりするキャラクター、そんなヘンテコな人物や状況を必死で演技する俳優、全体を通して怖くて不思議な雰囲気を醸し出す竹藪美術と照明のスキッとした暗さ、素朴で優しい音を奏でる音響や生演奏、誰かが命を失うたびに鳴る象徴的なししおどし。ししおどしの上を申し訳なさそうに少しだけ飛ぶ小鳥。
でも何がおもしろかったのかは一言ではまとめにくい。そういった諸々の要素が混ざり合って不思議なワールドを作っているので、その世界を体験したことがおもしろいと感じた。要素や情報が特別たくさんある、という訳でもないけれど、感想が散文的になる作品だと思った。どこから語っても、もやもやする感じだ。悪い心持ちじゃないけれど。
物語としては、創造神話的、おとぎ話的な世界観と生(性)死の話を軸にオカルトSF的コメディを融合させた点に注目した。
日本神話でイザナギとイザナミは天の御柱を回り、交わって国を生み落とす。産み落とされた子が淡路島や四国など日本列島を創っていく。ここには大いなる存在が大地を作り、人間や山や川を創ったという構造がある。自然に神が宿るという考え方だ。そんなアミニズム的ニュアンスを感じた。
山(竹林だけど)には死者が集まるという山岳信仰もある。太郎と加代の関係は黄泉の国のイザナミの話しのようでもある。その中で途中たけのこが生えるくだりもあったような。この物語の竹藪はそういった神秘の場所で、生と死の狭間として描かれていた。山姥のような野お母さんの役割は、人間がいる常世とは違う次元への入り口を静謐に守り、管理する山守(竹守)だとも言える。
山姥というのは、姥捨て山に捨てられた老婆への罪悪感から産まれた逸話だとか、山岳信仰ゆえに奉納の意図で山に入った巫女のなれの果てだとか諸説ある。野お母さんは人間を光線中で殺したり、人肉をハンバーグにして味噌汁に入れる恐ろしさを持っているけれど、何らかの哀しい理由があるのかもしれない。
野お母さんの正体はさらにSFの要素を含んでいく。後半で彼女が宇宙的な犯罪者だとわかる。冒頭に不時着した宇宙人たちに追われているという。宇宙の超高度な(時に間抜けな)技術を持った異星人がいて、彼らの技術をもって彼女というロボ?を地球に派遣しているという。
こうなってくると、かぐや姫宇宙人説のようなオカルトファンタジーのような様相を呈してくる。世界観としては諸星大二郎的なものを思い出したけど、表現のファニーさゆえに藤子不二雄の短編みたいな方が近いかもしれない。野お母さんは神話的な国生みの一連が終わってずいぶんと経ったあとのピクサーのウォーリーみたいな存在なのかもな、と思った。
表現のファニーさというのは表現の幼児性にあるのではないだろうかと思った。と言っても表現レベルが幼い、未熟であるということではなく、乳幼児が好みそうな表現が多い、ということだ。
宇宙人や野お母さんのかわいくて変な被り物、人を破裂させるほどの威力を持っている光線銃のおもちゃ。裏声や歌も含め「音」としてのおもしろさ(半濁音の楽しさなど)を含んだセリフ、登場人物の直情的で不条理な行動原理、「ちんちん」などの小学生が喜びそうな言葉。おとぎ話をモチーフにしている点もこれにあたるかもしれない。このパッケージが劇をどこか懐かしく愛らしく見せる。
一方、反復するやりとり(畳音、句法)が多いのも特徴だ。おかしみも生まれるけれど、かわいさや幼児さが強調されすぎていき、うっすら狂気的ホラーに変わる感じになるところもある。
そのようなファニーでちょっとクレージーな雰囲気をまといつつも、内容的にはヘビーな部分もある。一般的に思う乳幼児向けではない。自殺者の多い竹藪の話、男性と女性の唾あそびを宇宙人に見せる話。人肉入り味噌汁を食べさせる話は、昔話とかでありそうだけど。
そう考えると、子供の気持ちや感覚を刺激させつつ、不条理でシニカルな要素を楽しむ作品でもあるんだな、と思った。
劇中、竹林を抜けたら海が出てくる。海際に生と死の境があるというのは津波も原発被害も不穏な海外の動きも考えてしまう。北朝鮮に問合せをしてほしいという旨のセリフもあった。ついつい吹き出してしまいそうになるけど、現実が不条理になっているのも確かだ。普段、やたら身勝手で不条理な子供を馬鹿だなあと思うことがあるが、大人の方が馬鹿なところもあるわけで。変に技術力がある分、質が悪い。
技術と言えば、宇宙人の高度な技術の粋を集めた武器が吹き矢だったり、野お母さんが電池で動いていたり、ロボトミー手術みたいに脳を孫の手で掻いたり、クローン技術をコント風にした人間コピー機があったり、一見高度だが変な技術がよく出てきた。
これらは盲目的な科学技術発展への警鐘にも見える。変な宇宙人兄弟が地球をゴミのような星、人間を不要な存在だと言う視点もある。山本正典さんには世界がこのように不条理な世界として見えているとしたらおもしろい。怖いけど。
ミザンスとして、遠く暗く小さな、引きの絵が多かったのも特徴的だった。竹やぶの中だからかもしれないが、それゆえに、竹やぶの影というノイズが画面に常にあった。竹やぶのすれる音も断続的に耳へとノイズとして届く。観客と少し隔たりを持たせることで、登場人物の不条理なバカさ加減はやや冷静に見えてくる。すると、上記の怖さや、意味性が闇の中からゆらりと前に出てくる。
おもしろいやりとりが多かったのだけど、どこか、怖く、切なく、考えさせる雰囲気を助長したのはそのあたりの影響があったように思う。そういう演出を好む意味では以前までの作品よりもメッセージ性を強く意識させたい意図があるのかもしれない。
写真の音はリアルに冷たい音だった。境さんがケータイのカメラでよく写真を撮る。思い出依存のキャラクタライズなのか、魂を抜かれる比喩なのか、なんとなくすぐ写真取る人を残念だと揶揄しているのかわからないけど、シャッターを押す間とあの音で一瞬、観客と舞台の壁が取り払われる。この瞬間ファンタジーでなくなるような気がする。そういった効果がサブリミナル的に行われて、物語の死の雰囲気の怖さがちょっと自分の近く現実として寄ってくる感じがして、なんとなく怖いな、という不思議な感情も起こさせた。
おもしろくて、怖くて、不思議なのだけど、最終的には、野お母さんの月とのやりとり、三根とよしのイノセントな雰囲気の佇み方、冒頭に少し触れた加代の朝の日常への思い、これらの幻想的な情景がそのホラーやらを包み込んで印象に残る。最後にはネガティブなものよりも少しポジティブな気持ちになっていた。カッコンの音は、寂しいのだけど、寂しさの中にひとさじ程度の暖かみがある音だった気もした。
5月27日(土)11時の回に観劇。