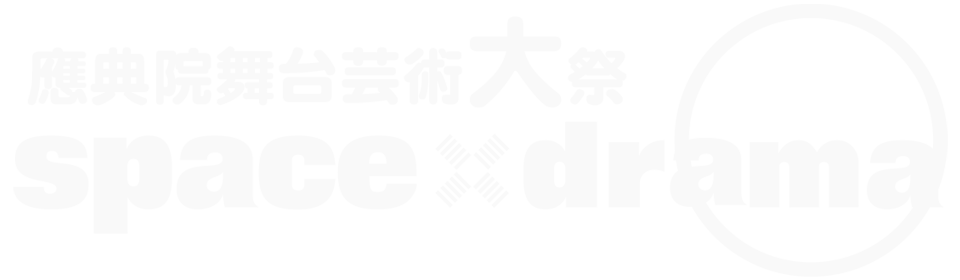【コトリ会議 「あ、カッコンの竹」】 ん、何となく生きている 【無名劇団 中條岳青】

山本正典さんの出ている舞台を初めて観たのは、劇団八時半の「むかしここは沼だった。しろく」だったと記憶している。繊細で危うく、鈴江さんの戯曲に抗うような佇まいが印象的だった。そんな山本さんが主宰するコトリ会議を、今回初めて観劇した。
竹藪の中では、ひとが死ぬとき、竹が鳴る、文学的で抒情的な世界。全体的に静かで、照度の低い舞台が、観る者に緊張を求める。芥川の「藪の中」のような、虚実が混在する不確かな物語を想像した。が、予想はよい意味で裏切られる。これは生と死の物語。
自殺は、劇的な題材ではある。死を目前にして、私たちはようやく生を意識する。そのありふれたモチーフは、学生演劇に蔓延している。私自身、高校生が紡ぐ舞台で、自ら命を絶った死者の語る言葉が描かれているのを多く目にしてきた。
あるとき、ふと気がついた。そのような劇中で死んでいく人はおしなべて、死んでから後悔し、死んでから悩み、死んでから幸せを求めていることに。つまり、死を目前にして、ではなく、死んではじめて、生を意識するのだということに。
生と死は不可逆なのだから、死ぬ前にもっと悩めばいいのに。私には、悩みたくないから、あれこれ考えたくないから死にたい、という甘えのように見えて、実に短絡的でくだらない、と思っていた。少なくとも、そこに生の葛藤や悶えはないと。
しかし、コトリ会議を観て、その考えは少し改められた。竹藪に現れる自殺志願者たちには、それらしい理由はない。何があったかは語られない。ただ、死にたい。死ぬことに迷いはない。むしろ竹藪に来た時点でもうすでに死んでいるのだ。
私たちは何となく生きている、何となく死ぬように。生と死は地続きで、それこそ、竹藪に迷い込むみたいに、人はいなくなる。死者は生者と語り、自分を傷つけては痛がり、過去をなつかしみ、そしてゆっくりと別れを告げる。生きながら、死んでいる。
ただ、どうしてだろう。関係ないけど私は悲しい。竹藪に消えていく人たちを思うと、悲しい。その思いを、竹藪の中で生きる二人の少女が代弁してくれる。死に行く人が鳴らす竹の音に、耳をすます彼女たちもまた、捨て子として、社会に抹殺されている。
夫と、死んだ妻の交わす会話が涙腺を刺激する。他愛ない思い出の断片の羅列が、かつて二人に生活があったことを物語る。人は死ぬから悲しいのではない、かつて確かに生きていたから、悲しいんだ。その微妙な差違を中高生に教える難しさを、つい考えてしまう。
黄色い宇宙人の兄妹や、花の被り物をした山姥に、昔下北沢あたりで観た、日常系のお芝居に急にイカの着ぐるみの人が出てくるみたいな、あの前衛的なのか古典的なのか分からない雰囲気を感じた。でも、絶妙に竹藪の緊張感を緩和していたと思う。
死は、安易に扱うものではない、とは思う。でも、事実として私たちの生はやすやすと軽んじられる。そんな世界を俯瞰で見下ろしながら、コトリ会議の舞台は、私たちのいる地点を優しく、愛おしく照らしてくれる。竹の鳴る音の余韻が、心地よい舞台だった。