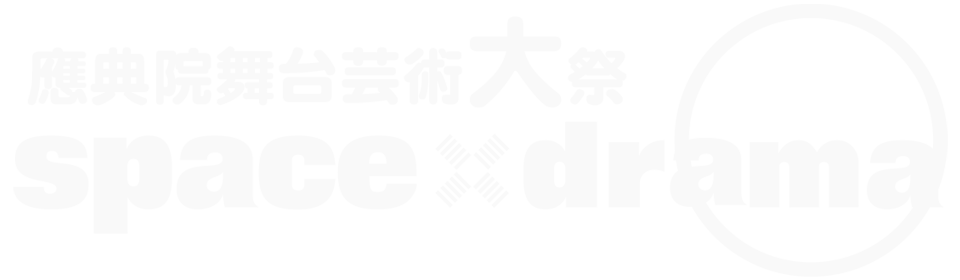【匿名劇壇『レモンキャンディ』】 始まる前からすでにオチていた 【泉寛介(baghdad café/ 脚本・演出)】

演劇作品を観るときにいつも演出、脚本、俳優、スタッフワークなどの区分に分けて創作側の技術の面から観る。本作品はある程度以上の基準にどれもが達していて、気持ちよさを覚える舞台だった。
10億kmから7日で落下する飛行船内における初期パニック後という突飛だけど独特なシチュエーション、導入暗転12カウント&悲鳴一連の効果、時間トリックや結構な八百屋舞台での俳優の緊張した身体と立ち振る舞い、音響・照明効果等、いろいろ注目すべきところがあるのだけど、人物が「愛すべきバカ(以下、愛バカ)」であるという初期設定を貫いている点をまず秀逸だと感じた。「愛バカ」であるという喜劇設定が、劇全体の温度や、その他の設定・状況をほぼ全てカバーする役目を担っていたように思えた。
「愛バカ」を書いたり、演出したり、演じたりするのは難しい。作品に関わる創り手は、本当は構造も内容も分かっている上でバカの振りをし続けなくてはいけない。観客にばれないために相応のリアリティが必要になる。このリアリティをどのように出すかが作劇上、目指すべきポイントだったと思う。
冒頭シーンのラスト、落下する飛行船の恐怖に混乱した女、ヨギリが飛行船の窓から外へ飛び降りると言い出す場面がある。観客は窓から出ると言う彼女を危ないと思う。だがここは落下する飛行船内であり、どうなるの?と思考が一瞬立ち止まる。結果、窓から外に出ても彼女は落ちない。まるで外に地面があって立っているかのように普通に外にいる。しかも真顔である。
どうやらガリレオの落体の法則のようにまったく同じ速度で落ちているのでそうなるらしい。このシーン、空気抵抗があることなど、無粋な言い方だけど現実的にはありえない。だから、マジか、ありえんやろと内心ツッコミが生まれ、観客に笑いがこぼれる。
このシーンは今回の作品の密室劇を成立させるために必要な要素、落ち行く飛行船から脱出は可能か、と言う命題を軽やかに処理しつつ、笑いという快の感情をプラスさせ、さらに次シーンへの期待感すら持たせていた。
通常、冒頭のシーンではそれぞれの役柄の説明と人物が置かれた状況をいかに巧く説明するかが重要だと思う。説明台詞で会話をしてもいいが、それでは会話にリアリティがなくなり、興がそがれる。ここでは緊迫感(予定された死への恐怖感)の深刻さ・リアリティが生きている。このフリの部分のリアリティは冒頭ラストに向かうまでの俳優の深刻な演技に依拠している。
今回のような突飛な状況だと俳優心理が納得せず、嘘への拒絶反応が出ることがある。俳優を深刻にさせるには、深刻になるべき理由が必要だ。SFやコメディではリアルでない設定の時があるため、難しい状況が生まれることがある。ここで「愛バカ」の手法が鍵となる。
「宇宙」を知らないというような、一般的にちょっとおバカな人物が、物事を知らないがゆえにパニックになる姿は、必死で深刻なのに喜劇的で、好感が持てる。
冒頭でドラマ、カルテットのようにレモン問答を続けるカイセイとドンテン。ドンテンの不安な若者みたいに、結果より経緯の選択・気持ちの共有を迫る感じ、それに対し何を言ってるかがわからず、すれ違うカイセイの感じ。2人のやりとりはピーピングライフの喧嘩カップルのように「愛バカ」だ。観客は、でも、あるよね、といった共感を覚え、愛着が湧く。スナアラシの「宇宙」の説明も「宇宙」を知らないことではなく、知らないことを知ったかぶりしようとする心理に共感し、愛され状態を作る。
冒頭ラストシーンは、この「愛バカ」が舞台上全員であるという初期設定ゆえに、俳優全員に真実味のある動機を持たせ、虚構的であるのに、深刻さも備えるシーンを作っている。だからあの真顔で深刻な状況なのに笑ってしまう。そしてこの笑いで煙に巻かれることで、飛行船落下の真実からミスリーディングさせる流れも多重的に作られている。この作劇の巧さに匿名劇壇の魅力は詰まっていると思う。
ただ、その手法ゆえに気になる点もあった。「愛バカ」の効果は全編に通じている。重い話題(死への恐怖、ドラッグ・セックス等へのモラルハザード、レイプなど身近で深刻な問題)を取り扱っている際に笑いが起こるシーンがある。笑いつつ胸にグサリと刺さる場面も当然ある。そういう表現で、観客の意見が割れるような瞬間がある。何が正しいのか観客の信念を揺さぶる。これは表現として、とてもいいことのように思う。
松本人志のドキュメンタルというamazon限定配信の実験的バラエティがある。芸人が持ち寄った100万円を供託し、ルール無用のにらめっこをするというものだ。本来「笑い」とはハッピーなものだけれど、この作品の中で芸人たちはじょじょに狂気的になっていく。賛否は今のところ両論だ。
なんでもないことが笑いにつながったり、過剰に性的なもの、暴力的なものや恐怖、低俗なものなど一瞬笑いに繋がらなさそうなものが大きな笑いや、やがて神聖さを帯びる瞬間もある。最後まで見ていると、「笑い」とは何かがわからなくなってくる。そんな錯誤の仕方に近いニュアンスがあったように思う。笑ってるけど、笑えるのかな、笑っていいのかな、みたいな感じだ。極度の緊張とタイムリミットまでの閉鎖空間、そこへ愛バカが集結するという構図でその番組を想起した。
匿名劇壇は虚構と現実のバランス調整ができる能力を持っていたように思う。実際常にビターなコメディと言った空気が新鮮に保たれていた。彼らはこの状況を作為的に作っている。この状況が、彼らの言う「ジョーク」っていう空間なんだろう。
また討論劇の要素もあった。理論展開も速いしセリフの情報量も多いと感じるところも多々あった。そこまでの速度や多さではないけれど、若い論客の論破合戦のような急き立てるニュアンスは受ける。だから全てを把握するのが難しい部分も多少ある。それを興味深い関係を匂わせたり、笑えたりするシーンに仕立て上げるのが巧いため、おもしろいのだけど、どう評価していいか迷う部分が出てくるという側面もある。
「ジョーク」なるものを楽しむ/楽しめるかどうかで匿名劇壇への評価は変わるんだろうな、と思った。
匿名劇壇は「ジョーク」への間口を広げるために、むしろ補完するように、メタフィクション的開き直り論とでも言うような手法も使っている。
SF的な設定の物語が展開されるとき、重箱の隅をつつくように観客が破綻を探す作業をすることがある。これは観客が整合性を取ろうと自然発生的に起こる現象だ。モラルハザードに対する反応もそれに当たるだろう。これっていいの?を探す探究心が沸き起こる。メタフィクション的開き直り論はこれら作業に対する防御にもなる。
脚本家、演出家である福谷圭祐さんはメタフィクションの化身のようなドンテンというフィクション症候群なる特殊な病に罹患している人物を物語に送り込み、この世界(劇世界であり現実)はフィクションかどうか分からない、とある種の開き直った態度を見せる。これを劇中で言われると、観客はこれが現実寄りなのかお芝居(虚構)なのか不安定になる。以降の表現を劇のお約束だから、みたいな片づけ方をする方へ傾く。
その結果、「愛バカ」による笑いで煙に巻かれたSF的破綻やモラルハザードへの探求作業は、演劇だからあり得るとか不謹慎とかある種どうでもいいや次元へと飛んでしまう。
時間・重力トリック等の科学的論拠、飛行船に呼ばれた理由等の謎、また人物たちのやり取り上の倫理的問題、社会問題も、この仕方で軽やかに処理されているように感じた。つまりSFのようでも社会風刺でも討論劇でもあるが、「ジョーク」であるこの作品の正体は、それらを揶揄したパロディ演劇ではないだろうか。
この作品はやたらと社会問題へのフックが多い印象も受ける。例えば、まさに「しゃかいもんだい」というワタユキが所属するアイドルグループ。歌詞が現代社会問題の皮肉になっているし、劇中の内容との関係性を考えたりしたくなる。
カルト宗教で育ったアマミズの性的虐待や閉鎖的コミュニティの末路との比較してみたり、哲学者ホッブズの自然状態を危惧する理論を髣髴させるドンテンを見て、正常と異常の区別や逆転に思いを馳せ、作品と金銭的価値に悩む同人作家スナアラシ・売買春問題を内包する高級娼婦のアサナギで貨幣の価値について考察したり・・・・・・、考えが羽ばたいてしまう点は随所に出てくる。
けれど、それらのシーンは次々にさらっと流される。深くまでは言及されない。やがて来る恐怖の前で、意味ない論が、討論にもならない形で会話されているのだろうか。シン・ゴジラの官僚会議の間抜けさをちょっと思い出す。
結局、すべては来るべき最大の恐怖=オチ(落ち)に対するフリでしかないように感じてくるのだ。極論だけど、匿名劇壇は訴えたいテーマを意図的に押し出しているわけでないと見える。
だが一方で、その態度が、逆に、訴えたい気持ちはあるけれど、まじめに訴えてもアレだし、訴える力もないし、結局訴えられない世の中だよね、過去作品「週末の予定」のように、それよりゲームしようぜピクミンしようぜ世界が終わるともそんなの関係ねえ、というような自身の状況に対するねじれた訴えとしてテーマが表出されている気もする。
そう考えると、意図的ではないのかもしれないが確固としたテーマが浮かびあがってきた。個人の人生の質や時間概念をどのように捉えるか問題だ。話の内容からそれは憶測されていたけれど、構造的にもテーマは符合する。
このテーマを考える際、補助線となるのは、今回の作品の最後まで結びつく最大のトリック、時間概念だ。登場人物は時間の概念にずっと振り回される。いったい時間が遅くなるとはどういうことか。
特殊相対性理論で言えば光速に近づくほど時間を遅く感じる。光速は時速10憶8,000万km。高度10億kmはここからきたのだろうか。でも光速に至ると人間って止まっちゃうんじゃなかったか。というか現実的に落下で光速に至るとは考えられない。となればこれは劇構造上のお約束として捉えるべきだろう。
とにかく超上空でそこから落ちていていずれ地表に達して全員必ず死ぬ。それまでの時間は7日間、そういうルールだ。チラシにも書いてある。その方がシンプルでいい。その上で、4日目で終わるというミスディレクションはずるいと思ってしまう。巧妙だけど。
速度を確認できる高度計測メーターは後半で型番だと分かる。つまり高度は10億kmでない可能性が濃厚だ。そうであったとしても、最低4日間は落ち続けているのだから、相当な高度であるはずだ。でも72~96時間以上落ち続けられる高度はそれこそ成層圏や月を軽く越えている。あり得ない。とすると、当人たちの時間感覚がすでに地上と違っていたのかもしれない。
ここでタイトルにもなっているレモンキャンディが仕事をする。ジャネーの法則(既知の事柄については体感時間が早くなる)、またゾウとネズミの法則(心拍数が速くなるので体感時間は遅くなる)の話を聞いたことがある。人間の脳や身体にはそのような事象が起こる。その機能を操作するドラッグ(集中すると体感時間が短く濃密になるというような脳作用の逆、脳を集中させず時間を遅く感じさせる)がその問題を解決する。
けれど最初はカイセイだけしか接種していないはずだ。とすると落下前の共同生活最初の数日のうちにカイセイがすでに当番のご飯にレモンキャンディを隠し味として入れていたのか。でもだとしたらカイセイの動機がわからない、地上のテレビの歌が聞こえるとか時間のずれは無いのか、・・・・・・なんかここらへんで、その辺り考えなくてもいいか、と思えてきた。
やっぱり、その辺りはドンテンのセリフに従って、時間の概念が変化することによって人生の質は左右されるというポイントを考えた方がよさそうだ。
この劇中の人物たちの思考の変遷は、時間の体感が論理上、1秒が一瞬にも永遠にも感じうるとされているので、一生が一瞬でもあり、90分でもあり、7日間(4日間)でもあり、無間地獄でもあると言う解釈が生まれる。
劇団活動を続けてきているモラトリアム意識が暗喩されているようでもある。自身の生を全うしているような、いないようなモラトリアムの期間はその最中にいるとき、永遠に感じられる。なのに、終わりが来ることだけは分かっている。終わりは必ず来る。メタフィクションを得意とする彼らはこの命題が芯を通っていることがよくある。
翻って僕らの一生もそうだと気付く。現在、僕たちが生きている今(死ぬまでの今)という時間は果たして濃密なものであるのか、今をよく生きるとは何か、死とは何か。
そういうものを感じさせるテーマを持つ作品だとも言える。
「落ちてないのかも(=時間が止まっているのかも)」のセリフに照明変化したような気がしたけど、その場面にハッとさせられたり、スナアラシとワタユキのゆっくりとした時間が流れる歌のやりとり、最後のライメイの筋トレを全員で見る最後の瞬間などグッとくるシーンもあったが、個人的に特に衝撃を受けたのは、上空8,000mで警告音が鳴り地上が見えると表現されたとき、今まで分かっていたはずの突然の死が急に目の前に飛び出してきた。
このシーンで、以前、應典院で日本航空123便墜落事故に関わるリーディングをやったことがあるのだけど、その資料集めをしていたときの恐怖がワッと蘇った。落ちていく航空機の中、気丈に闘った機長たちのボイスレコーダーから流ていた警告音。当時ずっと資料を読み漁り映像を見たりしていて精神的にちょっとまいってしまった。そのときの記憶に引っ掛かって心臓の鼓動が早くなった。
應典院という場の力もそこにはあったかもしれない。開演前にステキな美術だと思っていた舞台美術も、終演後、俳優たちが出て行ったあと、無人の飛行船は落下後の寂寥感を少し感じさせた。
本堂ホールに入ると、まずその舞台美術が大胆にお出迎えしてくれる。客入れの音響は落下や飛翔など作品世界と見事にリンクする邦楽のMixになっていた。ちょうど僕が見た回は始まる直前に「夢想花(♪とんでとんで)」、「DESIRE(♪まっさかさまに落ちて)」から「世界の終わり」のイントロが流れた。鮮やかなLEDで照らされた落下中の飛行船らしき美術を見つつ浴びる音はとても気持ちよかった。僕は滅びの美学的な切ないトリップをさせられて仕方がなかった。
ミッシェルが流れる中、すでに落下した後の彼らの残骸を最初からずっと見せられていただけだったんじゃないか。劇本編は偲ぶような回想だったのかもしれない。そんなことを後日思った。
5/20(土)19時の回に観劇