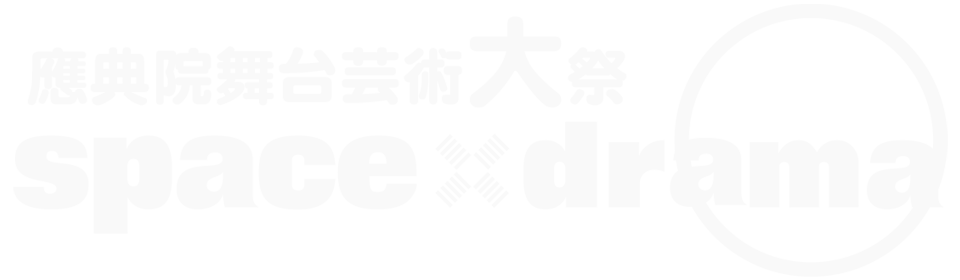【無名劇団『出家とその弟子』】 リア充女子は「超人」になりたいとか言いださない 【泉寛介(baghdad café 脚本・演出)】

宗教劇と聞いて、なんとなく身構えて観劇したものの、実際観てみると「善鸞」、「唯円」という2人の僧の悩みを軸にした青春恋愛メロドラマという感じで、思ったより親しみやすさのある作品だった。
冒頭、仏教用語での会話、パフォーマンスでスタートし、作品世界に対する期待感を煽られ、その後も割と昂ぶった感情を吐露するシーンが続く。序盤は情報がやや入ってきにくく、物語に入れない感じがしたが、善鸞と浅香、唯円と楓の関係性が見えたあたりで、ドラマとしては見やすくなった。
原作は唯円が主人公の感が強いけれど、本作品では善鸞が脚光を浴びている。恋愛要素に焦点を当てていて、原作よりとっつきやすい。その分、大の大人がそこまで恋愛や人生に悩むか?と感じてしまう部分もあった。まあドラマだからと言われたら身もふたも無いのだけど、不倫なんてありふれている時代に、じっと立ち止まり、純粋に悩み、煩悶する僧侶のドラマを見ると違和感が出る。
個人的な感覚だけど近代作家の恋愛作品は、不貞や、一途でない自身に対していつまでも懊悩する作品が多い気がする。この物語の「当時」は、鎌倉時代だけど近代でもある。そうなると仏教の話でもあるがキリスト教の話でもあると言える。
明治維新以降、国策としてキリスト教的な貞操観念が流入された。一夫多妻的な風習を持っていた「当時」のセンシティブな作家たちの戸惑いは「自由恋愛とは何か」、「女性の権利とは何か」という問いかけに向かったのかもしれない。
キリスト教と言えば劇中で多用されたマリリン・マンソンだ。浄土真宗とマリリン・マンソンはギャップを感じるが、考えてみると相当ハマっている。マリリン・マンソンの父はカトリックだった。父が親鸞である善鸞と被り、父が熱心な浄土真宗であった倉田百三とも被る。
マンソンは自身のアルバム名の通りアンチクライスト・スーパースターとすら称され、実際キリスト教者に批判を受けた。けれど彼はキリスト教の神そのものを否定はしていない。人々が崇め敬う神を否定している。それはニーチェのキリスト教批判に近い。ニーチェはキリスト教を社会的弱者のルサンチマン(強者への憎悪や嫉妬、現代で言うある種、病み?)の産物だと批判した。
後半の善鸞の復讐は親鸞に対してではなく、唯円に向かった。劇中ではその理由が父親鸞の自分に対する不信(すれ違い)に起因するよう描かれていた。親鸞の信を置く唯円を貶めることで親鸞に復讐する魂胆だろう。善鸞って女々しい。これは後述する男性化した女優の効果かもしれない。
それはさておき、これをマンソン的に捉えるなら、「権威」に対するルサンチマンとしての宗教への批判から来ているとも取れる。政治的階級社会の道理によって母親を切り捨てさせた浄土真宗という宗教、そしてそれが「権威」に対抗するルサンチマンでしかない宗教と善鸞が捉えていたならば、その嫌悪は相当だ。だから対象が親鸞でなくとも復讐は成立する。純粋な唯円が眩しかったという理由があれば善鸞の人間味が出て、尚いいかもしれない。
踊躍歓喜信仰への迷いの無さゆえ、冷徹に唯円や善鸞を責める悪役的な真仏房は、まさにThe Beautiful People(特権階級とか強者、偽善者的な意味でこの歌詞は訳せそう)なんだろう。唯円が善鸞と言葉を交わし、遊郭炎上に至る流れもコロンバイン高校銃乱射事件に通じるものがあると言ったら、言いすぎだろうか。唯円の中にも兄弟子たちへのルサンチマンがあるとすれば、兄弟子たちの苛めにあっている唯円も浮かび上がる。
善鸞の場合、母親への執着がとても強い。母を捨てた父の元から去り、母の面影として涼を追い、さらにその幻影を浅香に投影させる。全ての行動原理は母への愛情/もしくは愛情の欠乏とも言える。親鸞が最期を迎えるシーンで善鸞は仏を信じきれず、わからないと言う。マンソン的に言えば「仏自体を信じないことはない、人々の信じる仏は信じない」というところだろうか。
このシーン、後ろには遊女たちの元締めと一人二役である女優が阿弥陀如来として立っている。この元締めは遊女たち全員の母のような存在であった。後光の演出もあいまって、善鸞のルサンチマンもまた阿弥陀=「母」に浄化されたのだと捉えたら落ち着く。
マンソンの効果はそういう風に出てくるだろうか。単に性(マリリン・モンロー)と宗教(チャールズ・マンソン)に挟まれ受難を生きる登場人物たちの象徴としても分かりやすいが、ちょっと単純過ぎるか。
個人的には親鸞の玉日姫への気遣いを知らされたとはいえ、回心せず、最後まで完全にダークヒーローとして堕ちる方が好きだけど、今作品の方が確かに気持ちよくエンターテイメントとして観られる。
エンターテイメント性についても少し触れたい。割と文学的なイメージのある中條岳青さん作品の無名劇団は、今回そういった展開上でのエンターテイメント要素が入っていた。物語的に悲痛な裏切りはなく円満に収まる。
島原夏海さんの演出は身体表現を多用することが多い。場面転換が多い部分を布やコロスを使って対応していた。見た目に愉しいショーアップ的な演出だ。中條さんの作品がエンターテイメントに寄っている分、今回は以前までの無名劇団よりも違和感が少なかった。
ただ、この演出は俳優の技術を担保とするので、そこは気にしたい。
俳優の演技法はやや説明を優先するような方法を選択していたと思われるが、上記演出であれば、根本に複雑な内情を背負う役柄が多いのと、単語が難しく、座り芝居も多いので感情的・身体的な技術の俳優への依存割合は大きい。エンターテイメント路線に進むのであれば、この部分を今以上に特化したい。
女優の男役もあった。女優だけなら、ないしは完全に男女逆転ならコンセプトもわかりやすいのだが、今回は一部だけ、主要キャラクター2名を性転換させていて気になった。悩む男性というものに主眼を置き、純朴に悩む善鸞と唯円だけが男女逆転し、若い女優が男性として演じる。そういう意図で考えた。
女性が男性を演じる際、暴力的部分は柔らかな印象になる。悩み苦しむ状態を長く見せ続けられることへの抵抗は少ないのではないか。また男性化した女性が男性側の恋愛内情を語るという行為が、女性の理解し得る男性の仕方なさが演技として表出される。女性的男性の恋愛煩悶と言ってもいいニュアンスが出て、男性の中の女性性を際立たせていたようにも思う。先にあげた善鸞の女々しさはここから受け取れたようにも思う。
その中で唯円の楓に対するプラトニックラブについて少し思うところがあった。女性キャストによる中性的なキャラクター像が、ある種、セクシャルマイノリティ的な関係性を内包しているようにも感じ取れた。その意味で2人の社会的な隔たりを分厚くさせたように思える。階級や出自というものが他者と自己を隔てた時代から、社会的な立場や属性(LGBTQのような)によっても隔てられる現代だから発生する演出効果だと思う。
総じて、現代男性が他者と本質的な問題を解消することの容易でなさを意識させられた観劇だった。女性的男性(特に善鸞、唯円)の人間的弱さが露呈していた。信仰がどうこうよりも、結局根本に、人と人との関係のうまく行かなさが起因するという部分を考えた。
自己肯定感の少なさ=「愛されたい/愛されなさ」という観点から見ると、親鸞含め、善鸞と唯円、真仏でさえ、独りで何も決められない優柔不断男でコミュ障のようにも見られた。誰もニーチェの言う「超人(生の高揚を感じ、ルサンチマンなく生きる者、ある意味リア充)」にはなれない。こういう男性は現代、多い気がする。
対照的に遊女たちの決めぶりは鮮やかだ。自身が傷つくことも分かっていて、それを隠した上で、粋に、現実的に振舞う。遊郭が炎上した後、遊郭全てのことを担って真仏と唯円を追っ払った浅香や、すがすがしく「南無阿弥陀仏」を唱えている楓の方が、現実と宗教との距離を中庸で捉えている皮肉が本作にはあった。彼女らの方が僧侶よりも「超人」に近い。
5月14日(日)15時の回に観劇。